![]()
![]()
金属材料の機械的特性を知るための引張試験においては,破断までの荷重と変位の関係より,公称応力-ひずみ曲線を得ることができる.公称応力-ひずみ曲線からは,様々な機械的特性が得られ,力学特性の基本として用いられている.機械的特性のうち,延性については全伸び(破断伸び)として示されるが,均一伸びは最高荷重点における塑性伸びであり,塑性不安定条件により決定される.一方で,全伸びや局所伸びはn値やランクフォード値,ひずみ速度感受性指数などにより変化すると言われており,均一伸びのような明確な条件は存在しない.
「局所変形」もしくは「均一伸び以上の変形挙動」を整理することは重要であり,この局所変形について応力-ひずみ関係から考えると,局所伸びの大きさや局所変形中の公称応力-ひずみ曲線は試験片形状に大きく影響すると言われている.一方で真の応力-ひずみ関係の場合,通常の引張試験ではくびれが発生した以降(または,最高荷重点以降)の真応力と真ひずみを求めることは難しい.

局所変形中の真応力と真ひずみの推定については,1930年から1940年代にかけてのBridgmanらによる研究が有名である.Bridgmanの研究の背景として静水圧下での引張試験において局所伸びや絞りが増大するという結果があり,この点を明らかにするために破断直前までの真の応力-ひずみ関係を推定する手段について研究を行った.この時の引張試験は丸棒試験片を対象としており,不均一変形時の真応力を推定するBridgmanの近似式は以下に示すように,荷重とくびれの断面半径と曲率半径により計算することができる.
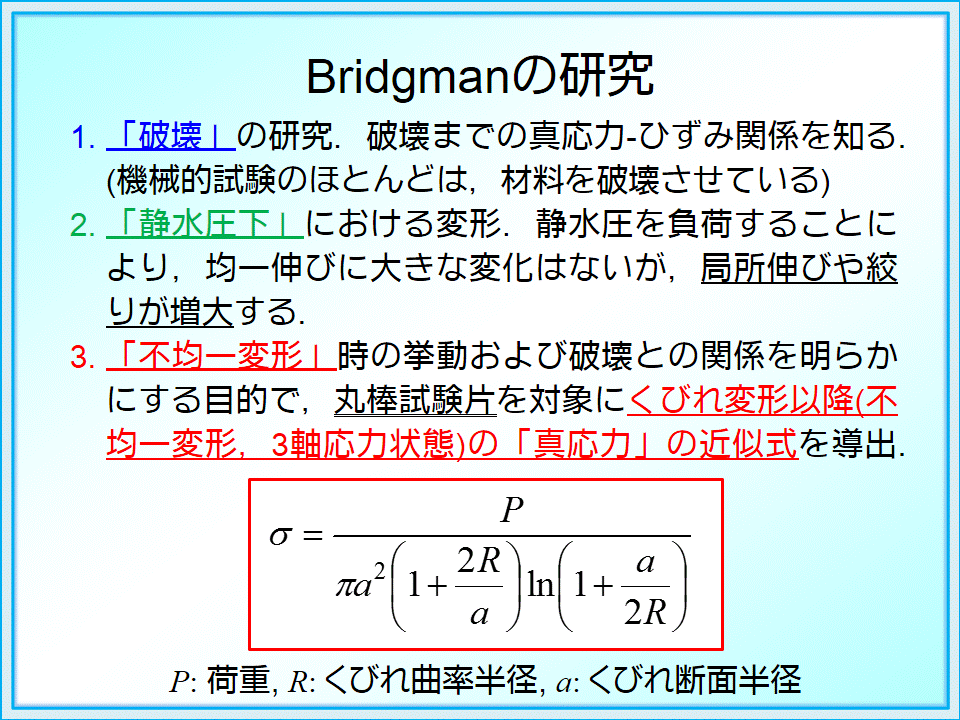
Bridgmanの式におけるくびれ以降の真応力の考え方としては,下の模式図に示すとおりとなっており,くびれの断面半径と曲率半径はそれぞれ図のように与えられる.くびれが発生した三軸応力状態における平均応力は荷重を断面積で割った値であり,場所によって大きさの異なる引張方向の応力は,場所によらず一定な値である「真応力」と場所によって変化する「静水圧引張応力」に分けて考えている.また,この時の真応力は相当応力に等しいと仮定している.
以上を簡単にまとめると,Bridgmanの式は真応力と平均応力の関係を表す補正式であり,いくつかの仮定を元に,くびれ部分の応力状態を単純化して導かれた近似式である.この時,「真応力」=「相当応力」であるという点と引張方向の応力の大きさがふたつの応力の足し算で記述できるという2点がBridgmanの式におけるポイントになる.また,この時の真ひずみは丸棒試験片の変形を考えているので,くびれの断面半径aを用いて計算できる.

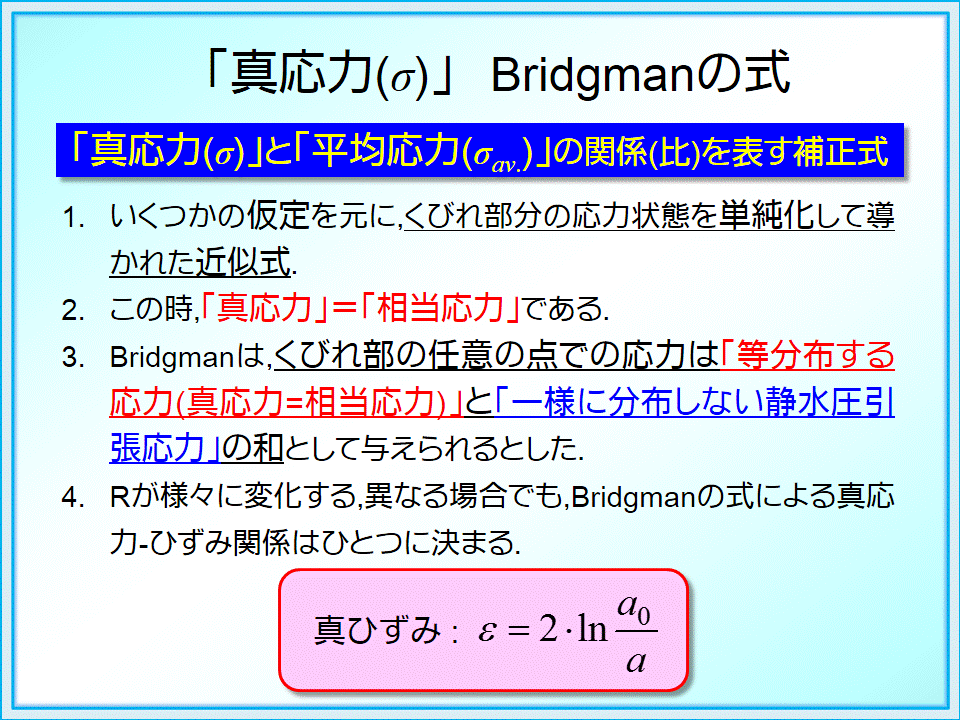
Bridgmanの式を用いた検討例として,Marshallらによる銅の研究がある.ここでは,破断まで引っ張った時と,途中でくびれ部を加工し,形状を変化させた時の真応力-ひずみ関係について検討した.途中でくびれ部形状を変えることでくびれ比であるa/Rの挙動は大きく変化するものの,計算された真の応力-ひずみ関係はひとつに決まることがわかった.これはBridgmanの式による真応力の大きさはくびれの形状によらないことを表している.
このような破断直前までの真の応力-ひずみ関係のデータは非常に少なく,局所変形含めた破断までの変形挙動を整理する手段として真の応力-ひずみ関係は非常に有効であると考えられる.以上のことから,我々はBridgmanの式を用いることにより破断直前,塑性加工限界までの真の応力-ひずみ関係の推定について研究を進めている.
「塑性加工限界」について,応力-ひずみ曲線の模式図を用いて説明すると(下図),左の「公称応力-ひずみ曲線」における×印は破断した点を示しており,この点は引張試験において真応力と真ひずみを推定できる限界と言える.以上のことから,「塑性加工限界」とは引張試験において真応力と真ひずみと推定できる限界点であると定義している.
